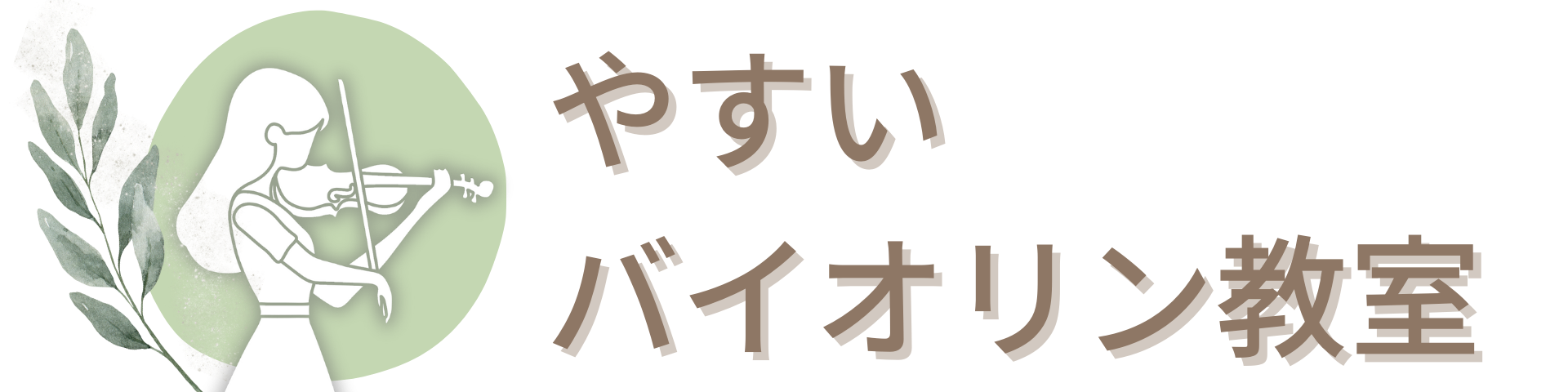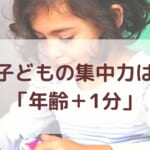【バイオリン練習】やる気スイッチを入れる声がけのコツ
保護者の皆様、お子さんの練習を促す時どのように声がけをされていますか? 「バイオリンの練習をしなさいよ~!」と言ってすんなりしてくれたら良いのですが、なかなかそうはいかないもの・・・。 今回はお家での練習の声がけについて考えていきましょう。 子供のやる気が出る言葉 ①一緒に練習しよう!と誘う 練習しなさい!と命令口調は反発したくなるものです。 練習を促す時はできるだけお子さんと同じ目線で声がけすることがお勧めです。 「一緒に練習しよう!」 「できないところはママも手伝うよ!」 こんな風に一緒に頑張ってみよう!いつでもサポートするよ!という気持ちで声がけしたいですね。 ②動画を撮って見てもらおう! 家族以外の誰かに演奏を聴いてもらうということはモチベーションに繋がります。 「喜んでほしいな」「びっくりさせたいな」という気持ちがバイオリンに向かわせます。 人に見てもらうために、上手に弾きたくて何度も練習するでしょう。 曲目のアナウンスをしてコンサートのように演出するのも良いですね。 ③今日はどれから練習する?(子供に選択権を渡す) 「今日はどれから練習する?」と選択権をお子さんに渡しましょう。 やる気を起こさせ、自主的な行動を促すには、自分で決めさせることが必要です。 一部でも自分で決められると人はやる気になります。 「どこが上手に弾けそう?」と得意な所から弾き始めるのも練習のハードルが下がってお勧めです。 ④ご家族がバイオリンを弾いてみる バイオリンを弾けないご家族がお子さんのバイオリンを借りて音を出してみましょう。 お子さんが「ここはこうやってやるんだよ!貸して!」と教えに来てくれるでしょう。 教える、ということでお子さん自身が気が付くこともあると思います。 言葉で練習を促すよりも、保護者がバイオリンに興味を持つことでお子さんのモチベーションを上がります。 ⑤練習しているね!と行動を認める 間違って弾いても、下手だと思っても「練習しているね!頑張っているね。」と行動を認めてあげましょう。 まずは「練習することが良いことなんだ」と理解させましょう。 お子さんの頑張りを認めた上で、「先生こうやったらもっと上手になるって言ってたけど、やってみない?」と提案するのも良いですね。 「練習しなさい!」という命令形以外の言葉で、上手にやる気を出させながら練習を促したいですね。 一緒に練習しよう! 動画を撮って見てもらおう! 今日はどれから練習する? ご家族がバイオリンを弾いてみる 練習しているね!と行動を認める お子さんの性格や環境に合わせて、様々な声がけをお試しください♪ バイオリンだけでなくピアノなどにも応用できます。 子供のやる気が削がれる声がけ ① 「練習しなさい」と命令する 人はもともと「自分の行動は自分で決めたい」という欲求が備わっています。 「練習しなさい。」と命令すると、抵抗や反発をしたくなるものです。 「練習しなさい」と命令されると嫌になるけれど、「おやつか遊びかバイオリン、どの順番でする?」と選択肢を与えられるとやる気になるお子さんが多いです。 お子さんのやる気を引き出すためにも「練習しなさい」以外の言葉で練習を促したいですね。 ②「~ちゃんはもっと練習してるよ!」と人と比べる 「お友達の方がもっとやっている」と比べる言葉はお子さんの自尊心を傷つけます。 「自分なんてダメなんだ」「練習しても無駄」とやる気を失ってしまいます。 誰かと比べるのではなく、今のお子さんの頑張りにのみ焦点を当てたいですね。 ③「練習しないと先生に怒られるよ!」と脅す 本来練習は自分のためにするもの。 「誰かに怒られる」が練習のモチベーションだと、何のために練習をしているか分からなくなります。 「なんで練習するんだと思う?」 「この練習をしたら、綺麗に弾けるようになるんだよ。」 と練習する目的をお子さんと一緒に話し合うことがお勧めです。 頑張ったことの先にどんないいことが待っているか、明るい未来に目を向けられると良いですね。 […]